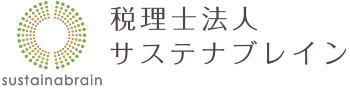私は、かつて、PwCアドバイザリーに勤務し、上場企業のM&Aに携わっていた頃、「HOYA」と「ペンタックス」の経営統合案件に関与した経験がある。2005年から2007年に掛けての出来事である。私は、ペンタックス側で財務デュー・デリジェンスを担当するチームのプロジェクト・マネージャーであった。当時協業したのが、同じくペンタックス側のFAを務めたモルガンスタンレー証券であった。
本件の経緯は後述するが、その時の両者の置かれた状況や交渉の経過が、この度の「ホンダ」と「日産」の経営統合問題と似ているところがあると感じた。
この2つの案件に共通するのは、事業価値或いは時価総額が大きく異なる者同士の経営統合であって、いずれも小さい方は、業績が悪化し自力での経営継続が疑問視されていたという点である。「HOYA」と「ペンタックス」の時価総額は2005年当時、「2兆円」と「1000億円」。20倍の差があった。「ホンダ」と「日産」の時価総額は足許で「7兆3000億円」と「1兆4000億円」。前者ほどではないものの 5倍以上の格差がある。また、当時の「ペンタックス」は、医療機器事業は一定の収益性があったものの、カメラや顕微鏡といった古くからの事業が極度の不振に陥っており経営を圧迫していた。現在の「日産」も、なかなか魅力のある新車を投入することができず、中国及び北米事業の業績悪化を主因として経営改善を迫られている。
「HOYA」と「ペンタックス」の経営統合の経緯
両者は、最終的には、「HOYA」が「ペンタックス」をTOBにより子会社化するという形で経営統合を果たしたのであるが、そこに至るまでには実は大変な紆余曲折があったのである。
「基本合意」に至るまで
「HOYA」は言わずと知れた光学機器・ガラスメーカーである。マスクブランクス、フォトマスクといった半導体製造素材などで世界トップシェアの製品を複数持つなど、当時から我が国有数の高収益企業であった。従来よりカンパニー制(事業部制)を採用し、各事業部があたかも独立した会社のように、移譲された権限をフル活用し、自由にダイナミックに世界を股に掛け経営を行っていた。財務マネジメント機能を欧州オランダに置き、グローバルでの資金及びタックスマネジメントを行い、また、当時まだ珍しかった委員会設置会社に早々に移行し、社外役員が過半を占めるなどコーポレートガバナンスにおいても先進的であった。一言で言えば「Excellent」な会社であった。
そんな「HOYA」は決して現状の高収益に満足しない。将来の新たな収益の柱として医療分野への進出を目論んでいた。
一方の「ペンタックス」は、こちらも得意のレンズ技術を活かした医療機器事業が成長しつつあったものの、伝統的なカメラや顕微鏡の事業が経営を足を引っ張っており、将来像を描きにくい状況にあった。すなわち、伸びしろのある医療機器事業を拡大させたいが、そのための資金力が不足していたのである。そんな両者をインベストメント・バンカーたちがマッチングさせた。
当初の統合スキームは「合併」であった。もちろん、存続会社は「HOYA」である。
両者の思惑
「HOYA」の狙いは最初から一貫して「ペンタックス」の医療機器事業であった。不採算で競争力が既に衰えつつあったカメラ事業などは不要であり、統合後に売却したいと考えていた。
一方の「ペンタックス」はと言うと、医療機器事業は統合後も自らがイニシアチブを取り、運営していきたい。加えて、伝統的かつ「PENTAX」ブランドの象徴でもあるカメラ事業を何とか存続させたいという強い意向があった。
一年半の期間を経て「基本合意」締結
この案件について私が最初に担当した業務は、「基本合意」のための事前調査であった。ノンアクセスによるデスクトップ・デュー・デリジェンスである。2005年の5月頃と記憶している。私は「ペンタックス」サイドであったため、相手方「HOYA」の財務状況を見に行くわけであるが、この時点では対象会社(HOYA)への接触が認められないため、有価証券報告書などの公開情報に基づく調査に限られた。調査は程なく終了し、クライアントである「ペンタックス」への報告も終えたが、その後、しばらく足踏み状態となる。ようやく、2006年12月に「経営統合に向けた基本合意締結」のプレスリリースが行われたのであるが、検討開始から1年半を超える期間を経て、ようやく一定の合意に至ったことになる。
私はFAではなかったので詳細は分からないが、恐らく、「ペンタックス」のカメラ事業の取り扱いが焦点となり、協議が長引いたものと思われる。基本合意書では「互いの事業の存続」が謳われた。この文言を入れなければ、カメラ事業を売られてしまうのではないかと疑心暗鬼になっていた「ペンタックス」を説得できない。この時点では一旦「HOYA」が折れた形となった。
正式なデュー・デリジェンスの実施
基本合意後、正式なデュー・デリジェンスが始まった。当時「HOYA」の本社は西武新宿線・下落合駅から少し歩いた住宅地にあり、時価総額2兆円の会社にしては地味な本社ビルであった。私率いる財務デュー・デリジェンスチームはその本社へ何度も赴き、経理部やCFO、各事業部長やCEOへもインタビューを実施した。
 (HOYAの旧本社・新宿区中落合)
(HOYAの旧本社・新宿区中落合)
財務デュー・デリジェンスを行うと、通常、資産の含み損や簿外債務の存在などが検出されるが、「HOYA」においては問題とされる事項は殆ど検出されなかった。その代わり、事業性評価、撤退ルールなど厳格な経営管理制度についてヒアリングすることが出来た。なるほど、この仕組みがここまでの高収益企業に成長した会社の経営基盤かと、大いに勉強になった。一方で、その緻密さ、厳格さには、ある意味、恐ろしさも感じた。
その後、調査結果をレポートに纏め、クライアントである「ペンタックス」に報告した。含み損などの検出事項はほぼ無かったため、参考情報として、「HOYA」が採用している事業性評価、撤退ルールを含む経営管理の手法・制度についても説明した。
経営陣に報告した後、社員向けにも説明して欲しいとの依頼があった。デュー・デリジェンス結果を一般の従業員向けに説明するなどということは通常は無いことである。後日、再度「ペンタックス」本社に呼ばれ、多くの一般社員が集まる食堂に通された。私は、経営陣への報告と同じ説明を一般社員向けに行った。雰囲気は暗く、質問等は一切出なかった。その時、多くの社員の方々が思ったに違いない。「HOYAと合併したら、一体うちはどうなってしまうのだろう。」と。
 (ペンタックス本社・板橋区前野町)
(ペンタックス本社・板橋区前野町)
「ペンタックス」経営陣の迷走
デュー・デリジェンスを経て、合併の最終合意に向け、詰めの協議が行われるはずであったが、ここから「ペンタックス」経営陣の迷走が始まる。なんと、「HOYA」との合併を撤回すると宣言したのである。同時に社長交代が発表された。
これまで統合を推進してきた当時の社長が取締役会での動議で解任されたのである。まさか、私の調査報告書に含まれていた「HOYA」の徹底した事業性評価、撤退ルールに怖気づいたのか。このまま合併すれば完全に飲み込まれる。自分たちのアイデンティティでもある「PENTAX」のカメラ事業も売られてしまうとの恐怖感に襲われたのか。
一部報道では、「ペンタックス」の一部株主が合併比率に不服の意を表明していることが原因とされている。それも確かにあったのかもしれないが、主因は「ペンタックス」経営陣の「保身」にあったと私は見ている。
業を煮やした「HOYA」は統合スキームを『TOBによる「ペンタックス」の子会社化』へと舵を切る。「より高いプレミアムを付け、ペンタックス株主の支持を取り付けるため」とは表向きの説明であり、「HOYA」にとっては子会社化の方が、力関係・支配関係を明確にできるため、むしろ都合が良かった。
それでも「ペンタックス」は抵抗した。前社長を解任し残った取締役たちはTOBに賛同せず、単独での生き残りを前提とした中期経営計画を発表したのである。そもそも、単独での将来像が描けなかったことが本件の発端であったはず。「ペンタックス」経営陣は自らの「保身」のために、合理的に判断を下す能力を失っていた。
案の定、単独での生き残り策は大株主の理解が得られず、株価は下落。選択肢を失い、止む無く、「HOYA」によるTOBを受け入れると表明した。前社長を追い出した取締役たちも総退陣することとなった。
「ペンタックス」の末路
「HOYA」による子会社化後、間もなく「HOYA」が「ペンタックス」を吸収合併し、法人格としての「ペンタックス」は消滅した。設立から70年の歴史に幕を閉じることとなったのである。
「HOYA」が手に入れたかった医療機器事業は一つの事業部として組み込まれ、懸案のカメラ事業は、しばらくしたのち、「PENTAX」ブランドを冠したままリコーに売却された。リコー傘下で今も「PENTAX」ブランドのカメラは存続しているものの、残念ながら、カメラ市場での存在感は無いと言っても過言ではない。
かつては、有力な光学機器メーカーとしてレンズ・カメラ業界の一翼を担ってきた「ペンタックス」。今でこそ、スマートフォンの普及に伴いカメラの需要が縮小し、各社とも事業構造の変革を経て今に至るが、当時まだ、スマートフォンも無い時代。競争力の弱まった本業(カメラ事業)の梃入れが後手に回ったことで業績不振に陥り、折角、収益事業に成長した医療機器を他社に奪われ、挙句の果てに会社が消滅し、唯一残るブランドも風前の灯火。悲しい限りである。
これもすべて、経営陣の責任。全社的におっとりした社風で、急な変革などへの耐性も無かった。会社を変えられなかったのはやはり歴代経営陣の責任なのだと思う。
「ホンダ」と「日産」の案件に共通点
翻って、最近話題となった「ホンダ」と「日産」の経営統合の破談。「HOYA」と「ペンタックス」のケースに似た点が少なからず見られる。
「HOYA」と「ペンタックス」の例ほど極端ではないが、事業価値・時価総額に大きな差があり、小さい方(日産)は経営難。単独での生き残りが厳しいはずなのに、取締役は危機意識を欠き、踏み込んだ再建策も立てられない。自らの実力も顧みず「対等」に拘り、交渉をこじらせる。業を煮やした「ホンダ」は子会社化に舵を切り、結果「破談」。
今後、「日産」がどうなるか、目が離せない。
自浄能力の無い組織は滅ぶ
1990年代後半に極度の経営不振に陥った「日産」はカルロス・ゴーンを社長として招聘し、一旦は再生を遂げる。が、のちに、その立役者を追い出し、今また迷走している。その間、法律に抵触するような下請けいじめなども発覚し、組織全体として根深い問題を抱えていると思われる。
自らを客観的に分析し、環境変化に対応すべく、進むべき方向付けを行う。そして変革を断行する。こうした自浄作用が機能しない組織はいずれ滅ぶ。それには、役員のみならず従業員一人ひとりの意識が変わらなければならないのであるが、全社的な意識改革を促すリーダーシップ、仕組み作り、次世代経営人材の育成は やはり経営者の仕事なのである。