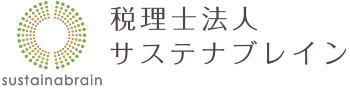2025年10月9日(木)、日本公認会計士協会東京会が主催する「第51回 公認会計士フォーラム 栃木大会」が、宇都宮市内の「ホテル東日本宇都宮」で開催されました。
プログラムの中の「事業報告 ― 地元で活動する公認会計士」で講演の機会を賜りましたので、今回はその内容をご紹介したいと思います。
Today’s Agenda
栃木県における私の公認会計士としての活動のメインは「事業再生支援」であります。よって、本日は、私の「事業再生支援」業務についてお話しさせていただきます。
前職はPwCアドバイザリー
栃木・宇都宮で独立して5年が経過したところですが、独立前は、「PwCアドバイザリー合同会社」という会社で、「M&A関連業務」及び「事業再生支援業務」に15年以上従事しておりました。途中、事業会社への出向や、海外駐在なども経験しました。PwCアドバイザリーでは、M&Aでも事業再生でも、クライアント又は対象会社は、基本、上場企業でした。日経新聞にドーンと載るような、大規模で、華やかな案件が多かったです。
そして、2012年にメインの業務が「M&A」から「事業再生」に変わり、そこで初めて「“経営”に向き合っている」という感覚を覚えたことを記憶しています。過去に経験した監査業務では、自分自身がまだジュニアだったこともあり、クライアント全体を見るというより、部分的な関与にとどまり、どうしても局所的な視点に陥りやすかったと思います。また、M&A関連業務では、本質的に、クライアントとターゲット(対象会社)が異なるということもあり、また、方法論、交渉術、法規制などテクニック論に走ってしまう傾向にあり、クライアントの「経営」について深く考えることは正直ありませんでした。
ところが、ひとたび「事業再生」の世界に身を置くと、リストラや資金繰り対応にとどまらず、「経営課題」や「事業戦略」についても深く関与することになり、正に、社長目線でクライアントと同じ土俵で考えることが求められます。同じ会社の中でも部門が異なると、こうも違うものかと、新鮮に感じたことを覚えています。
蛇足ですが、実は、長年、宇都宮から東京まで、新幹線で毎日通勤しておりました。
独立
そんな中、2020年(今から5年前ですが)、コロナが流行り出し、リモートワークで会社に行かなくなりました。そこで色々と考える時間もでき、「そろそろかな」と思い、「退職」と「独立」を決意しました。
もともと、高校3年の時に公認会計士を志した当初から、ゆくゆくは地元栃木で独立したいと考えていましたので、独立のタイミングとしては大分遅くなりましたが、ようやく「初期の志を果たす」ことになりました。
ゼロ開業。取り敢えず、アドバイザリー業務で食っていこう。
税理士登録もしましたが、顧客ゼロ、収入ゼロからのスタートです。
税務顧問先などはすぐには増えないと思っていましたので、とりあえず、これまでの経験を活かして、M&Aや事業再生支援などのアドバイザリー業務で食っていこうと思っていました。
ちょうどコロナで、中小企業経営が大変と言われていた時期でしたので、少なからず事業再生のニーズはあるのではないかと思っていました。
最初の一歩。それは同業者を頼ることでした。
ただ、「自分はできる」と思っていても、どこから仕事をもらうかが問題です。これまでずっと東京をベースに仕事をしてきたため、何のコネクションもありませんでした。
そこで頼ったのが同業者でした。当時、栃木県公認会計士会の会長だったK先生。昔から存じ上げていましたので、取り敢えず独立開業の挨拶に行きました。「事業再生やりたいんです。」と言うと、「それならS先生を尋ねなさい。」と言われました。それまで私はS先生とは面識がありませんでしたが、S先生は県内の「事業再生の第一人者」でありました。
S先生の事務所に挨拶に行きました。そこで、こんなことを言ったら嫌な顔をされるんだろうなと思いつつも、私も必死でしたので、勇気を振り絞って言いました。「銀行の人を紹介してもらえませんか?」
幸いにも、S先生からは、快く、「いいですよ!」と言っていただきました。銀行のほか、中小企業再生支援協議会(現在の中小企業活性化協議会)の統括責任者の方や信用保証協会の方も紹介していただきました。本当に有難かったです。こうして、仕事を貰うための「最初のきっかけ」を頂けた訳です。
再生支援業務の概要
さて、私が行っている再生支援業務は、金融機関から直接、頂くこともありますが、大部分は「栃木県中小企業活性化協議会」の「外部専門家」としての業務になります。
通常のリスケ案件であれば、まずDD(デューデリジェンス)をやって、次に計画策定、その後、伴走支援というステップになります。
協議会案件の場合、DDは「財務」に加えて、「事業DD」(いわゆるビジネスDD)も必要となります。事業DDは通常、中小企業診断士が担うことが多いのですが、私の場合、有難いことに、財務だけでなく事業DDもセットで依頼されることが多いです。前職時代を含めて、事業DDは本格的にやったことがありませんでしたので、最初は試行錯誤で、かなり時間が掛かりました。事業DDは今でも苦労しますが、その後の「改善施策の立案」「実行支援」を行う上で、「事業に関する考察」を自分でやるというのはすごく有用だと思っています。
会計士的な発想で、DDと言うと、とかく「実態純資産」とか「正常収益力」という話になりますが、それは飽くまでDDの一部に過ぎません。
重要なのは、「窮境に至った背景」や「問題の真因」を明らかにして、更に、再生に向けた「改善の方向性」を示すことになります。これがバシッと言えていないと、何の価値もないDDレポートになってしまいます。
そして、計画策定では、DDで挙げた「改善の方向性」を具体化させて、数値化し、計画書を取り纏めていきます。途中、メインバンクとも相談しながら、内容を詰めていきますが、実態債務超過解消まで何年を要するか、債務償還年数はどの程度改善するか、現在止めている借入元金の返済はいつから再開できるかなどがキーポイントとなります。
計画が完成すると、バンクミーティングを開催して説明を行います。質疑応答を経て、最終的にすべての債権者から同意書を取得して、晴れて「計画成立」となります。
業務報酬
業務報酬は、私の場合、案件に拠りますが、事業・財務のDDと計画策定で300万円前後というケースが多いです。そして、報酬の3分の2が国から補助金として出るというのがポイントです。従って、事業者負担は100万円で済むことになります。これは本当に有難い制度です。資金繰りに窮している中小企業が普通300万円も出せないですからね。
伴走支援報酬は「企業の規模」や「サポートの内容」に拠って異なります。私の場合、月3万円というところもあれば、月20万円頂いている案件もあります。
そのほか、協議会スキームに乗らない案件については、「経営改善計画策定支援事業」(通称:405事業)と呼ばれる中小企業庁の制度を使うことになりますが、これも同様に3分の2の補助金が出ます。こちらは、伴走支援報酬についても3年間に限り補助が出ます。
再生の「壁」
こんな感じで各案件を進めていく訳ですが、問題は、「我々公認会計士が関与して、本当に再生するのか?」 ということです。どうやったら、破綻しそうな中小企業を再生できると、皆さん、思いますか?
リストラだけでは再生は困難。とにかく、PLを改善させること
債務免除などの抜本的な金融支援がある場合でも、抜本支援がない通常のリスケ案件でも、同じですが、とにかくPLを改善させなきゃいけないということなんです。借入金の返済に窮してこうなってしまっている訳で、過剰債務を解消できるだけの「十分な利益が出せる体質」にしないといけないんです。
じゃあ、どうやってPLを改善させるのか。
再生の切り札「値上げ」
様々な切り口で「改善策」を練って、実行していく訳ですが、最近のトレンドは「値上げ」です。様々なコストが上昇しているのに価格転嫁できずに、収益性が悪化してしまっている中小企業がかなり多いです。
ここで値上げを実行できるか/できないかが再生できるかどうかの分岐点になります。
値上げしても、それを顧客に受け入れてもらえる会社は再生できます。一方、これが出来ない企業があります。或いは、値上げしたら途端に売れなくなるというケースも。こういう企業の再生はなかなか「難しい」と感じています。
コスト上昇の中でも一番悩ましいのが賃金です。今後も継続的に上昇が見込まれます。「労働集約型」のビジネスは益々厳しくなると思います。
もともと、日本の中小企業は「生産性が低い」と言われています。要因としては、「人材の流動性が低い」「優秀な人材が集まりにくい」「デジタル化の遅れ」などが指摘されていますが、そんな中小企業においても、これからは、生産性を高め、「付加価値」を上げていかなければなりません。どうやって「付加価値」を上げていくか、これは、中小企業「共通のテーマ」でもあると思います。
そして、この中小企業の「付加価値向上」という大きな課題に、我々公認会計士が、正面から向き合う必要があるのではないでしょうか。
再生支援業務まとめ
以上、纏めますと、再生支援業務は、企業の「経営」に深く関わる業務です。社長と同じ目線で、自分事として一緒に考える姿勢が求められます。そして、一定の方法論もあり、やや専門的です。大変です。疲れます。Excelで複雑なモデルを組んで回すことは基本中の基本。タイトなスケジュールに追われるし、何よりも税理士業務との掛け持ちは結構ハードです。
でも、面白いです。遣り甲斐もあります。報酬も悪くないですし、何より、これからどんどんニーズは増していきます。
栃木県における課題
最後になりますが、我々栃木県会は、一つ、問題を抱えております。それは、「事業再生が出来る会員が極めて少ない」ことであります。県内でこの分野の第一人者であるS先生そして私を含め、現在、数人程度しか事業再生ができる人材がいないというのが今、問題となっています。
従って、若い世代の会員に一人でも多く、この世界に入ってきてもらいたい。そして少しでも早く一人前になれるよう、ナレッジの共有や勉強会、保佐人制度を使った共同デリバリーなどを実施できればと思っています。
私からの報告は以上になります。ご清聴ありがとうございました。