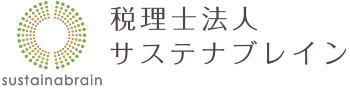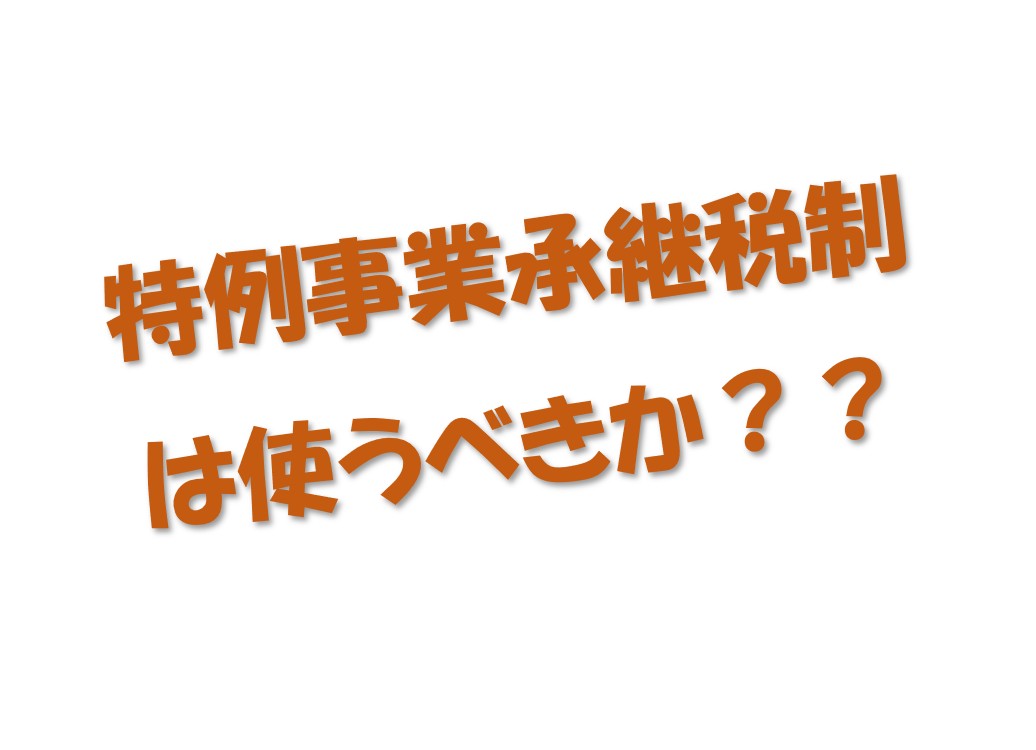
中小企業の経営者にとって、事業承継は避けて通れない重要課題です。
特に、自社株式を後継者へ引き継ぐ際には、多額の贈与税・相続税が発生し、承継の大きなハードルとなります。
この税負担を大幅に軽減するために設けられたのが「法人版事業承継税制」です。
今回は、「一般措置と特例措置の違い」から、申請期限が間近に迫る「特例措置」の適用要件・手続・スケジュール・活用判断までを、実務に即して解説します。
| 目次 |
1. 法人版事業承継税制とは
法人版事業承継税制とは、非上場会社の株式を後継者が贈与または相続により取得する際の贈与税・相続税を猶予または免除する制度です。
中小企業の円滑な事業承継を促進するため、一定の条件を満たす場合に贈与税や相続税の納税を猶予し、経営継続が一定期間続いた場合は免除されます。
この制度には、次の2つの措置があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般措置 | 恒久的な制度(平成21年度創設)。要件は比較的厳しく、猶予割合は80%。 |
| 特例措置 | 平成30年度税制改正で創設された時限的制度。要件が緩和され、猶予割合100%。2027年12月までに承継が必要。 |
2. 特例措置の概要
次に、特例制度について詳しく見ていきます。特例制度の特徴は何と言っても、納税の猶予割合が100%である点です。
(1) 制度の目的
中小企業の経営者が高齢化する中で、後継者へのスムーズな承継を促すため、税負担を実質ゼロに近づけることを目的としています。そのため、猶予割合が100%となっています。
(2) 適用の対象となる会社
特例措置は、以下の条件を満たす中小企業者(非上場会社)が対象です。
- 資本金または出資金が1億円以下
- 上場会社や風俗業・資産管理会社などを除く
- 常時使用する従業員が1名以上(家族従業員を含む)
(3) 適用の対象となる株式
先代経営者が保有する自社株式で、後継者が一括で取得するものが対象になります。
(4) 特例措置の主な特徴
一般措置と比較すると下表のような特徴があります。
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 対象株式 | 発行済株式総数の3分の2まで | 全株式 |
| 後継者数 | 1人 | 最大3人まで |
| 贈与・相続時期 | 制限なし | 2018年1月〜2027年12月まで |
| 税負担 | 贈与税・相続税の80%猶予 | 贈与税・相続税の100%猶予 |
| 雇用維持要件 | 5年間で8割維持(厳格) | 緩和・形式的要件に変更(実質的に撤廃された) |
| 相続時精算課税の適用 | 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与・推定相続人等以外の適用も可 |
| 特例承継期間後の減免要件 | 民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除 | 左記のケースに加え、譲渡・合併による消滅・解散時も再計算し、超える部分の猶予額を免除 |
| 提出書類、提出期限 | 随時認定申請 | 事前に「特例承継計画」提出が必要(2026年3月末まで) |
| 贈与期限 | なし | 2027年12月末まで |
ご覧の通り、全株式が対象となり、後継者も1人に限られず3人まで、雇用要件の緩和、相続時精算課税制度の適用範囲の拡大、納税額が減免されるケースが増えたことなどが、一般措置に比べて優れている部分となります。
一方で、制限があります。贈与または相続の時期が2027年12月までと時限的な措置とされており、何よりまず、2026年3月末までに「特例承継計画」の提出が必要である点に留意が必要です。
3. 特例措置の適用要件
特例措置を受けるためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)会社の要件
① 中小企業基本法に定める中小企業者であること
中小企業基本法に定める中小企業者の定義は、業種ごとに「資本金」と「従業員数」を基準として定められています。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
「資本金基準」と「従業員数基準」はどちらかを満たしていれば、中小企業者となりますので、例えば、小売業で資本金が5,000万円を超えていても、従業員数が50人以下であれば大丈夫です。
② 上場していないこと
③ 性風俗関連特殊営業に該当する事業を営んでいないこと
④ 子会社、特別子会社(いわゆる兄弟会社)が上場会社、風俗営業会社または大法人でないこと
⑤ 資産管理会社や休眠会社でないこと
⑥ 常時使用従業員数が1名以上いること
⑦ 第一種特例経営承継受贈者以外の者が拒否権付き株式を保有していないこと
(2)先代経営者の要件
① 贈与・相続前に代表者であったこと
② 総議決権数の過半数を保有していること
③ 贈与時に代表者を退任していること(贈与時より前に退任していてもOK)(相続後には代表を退任すること)
④ 一定数以上の株式等を贈与または相続すること
(3)後継者の要件
① 贈与・相続により、第一種特例経営承継受贈者とその親族などで議決権の過半数を保有すること
② 後継者が1人の場合、同族関係者の中で最も多く議決権を有していること
③ 18歳以上であり、贈与・相続により代表者に就任すること
④ 贈与・相続後、継続して株式を保有し、継続して会社を経営する意思があること
⑤ その会社の株式等について、一般措置の適用を受けていないこと
⑥ 特例承継計画に記載された後継者であること
親族外への贈与にも相続時精算課税制度の適用が可能
事業承継税制の利用に際して、暦年課税制度ではなく相続時精算課税制度の適用を受けることが可能ですが、相続時精算課税制度の適用対象者は原則として推定相続人と孫とされています。しかし、特例措置においては、推定相続人と孫以外の親族や第三者であっても相続時精算課税制度の適用を受けて納税猶予の適用を受けることができます。
4. 特例措置の手続とスケジュール
制度を利用するためには、複数の段階的な手続が必要です。
特に、「特例承継計画」の提出期限(令和8年3月31日)を逃すと、特例措置の適用ができなくなります。
(1)特例承継計画の提出(最重要)
- 提出先:都道府県(認定経営革新等支援機関の確認が必要)
- 提出期限:2026年(令和8年)3月31日まで
- 内容:会社概要、後継者予定者、承継時期、今後の経営方針などを記載
※この時点では実際に贈与・相続していなくても構いません。
(2)贈与・相続の実行
- 贈与の場合:2018年1月1日〜2027年12月31日の間に贈与を行う
- 相続の場合:同期間中に被相続人が死亡した場合に適用対象
(3)都道府県知事の認定申請
- 贈与・相続後、申告期限の2か月前までに都道府県知事の認定を受ける必要があります。すなわち、贈与がなされた場合は、贈与を受けた年の翌年1月15日までに、また、相続が発生した場合は、相続発生後8か月以内にということになります。
- そして認定書を取得後、税務署に提出して贈与税または相続税の申告を行います。
(4)継続届出
- 承継後5年間は、毎年1回「継続届出書」を税務署に、「年次報告書」を都道府県に提出する必要があります。
- また、5年経過後は、3年に1度、「継続届出書」を税務署に提出する必要があります。
まとめると、下図の通りとなります。

5. 納税額が免除されるとき/納税猶予が打ち切られるとき
100%の納税猶予とは飽くまで「猶予」であって、「免除」されているわけではありません。では、どういうケースで納税額が免除されるのでしょうか?
贈与税の納税猶予を受けている間に先代経営者が亡くなると、猶予されていた贈与税は免除されます。但し、贈与税が猶予されていた対象株式等については、先代経営者から後継者に相続があったものとみなして贈与時の評価額で相続税が課税されます。その際、一定の要件を満たせば、切替え手続きを行うことにより対象株式等に係る相続税について納税猶予を継続することが可能です。すなわち、「贈与税の納税猶予」から「相続税の納税猶予」にスイッチされる訳です。
では、猶予された相続税はその後、どうなるのでしょうか?
相続税が最終的に「免除」される主なケースは以下の通りです。
免除される典型ケース
会社が承継後も事業を継続し、後継者が代表・株式保有を維持したまま寿命を迎えた場合
「制度の想定どおり、後継者が一生代表兼株主として経営を続けた」パターン。後継者の代でこの制度が完結したとみなされ、この場合、猶予税額は免除され、課税は発生しないこととなります。
逆に、納税猶予が打ち切られるケースとしては以下の状況が挙げられます。
納税猶予が打ち切られるケース
- 後継者が 代表取締役を辞めた。
- 後継者が 株式を譲渡・売却した(担保に入れた場合も注意)。
- 会社が 資産管理会社化してしまった。
- 継続届出書の提出を怠った。
- 雇用維持要件(従業員数の8割維持)について、やむを得ない事情と認められない場合。
上記のような場合には、猶予されていた贈与税・相続税が一括で課税されます。更に、猶予されなかった場合の本来の納期限から起算して利子税も課税されます。
以上、大きな優遇が得られる一方で、様々な制限があるのも事実です。改めて、特例措置のメリットとデメリットを整理してみましょう。
6. 特例措置のメリット
- 贈与税・相続税が実質的にゼロに
- 自社株評価が高い会社でも、税負担を心配せず承継可能
- 複数後継者への承継が可能
- 兄弟や子どもなど、最大3人までの共同承継が可能
- 雇用要件が緩和されている
- 人員削減や外部要因による雇用変動でのペナルティが実質的に撤廃
- 金融機関にも好印象。計画的な事業承継が進んでいる会社は、信用面でも高評価となりやすい
7. デメリット・留意点
- 廃業・株式譲渡で猶予が打ち切り
- 経営継続が前提。譲渡・解散等があると一括納税
- 手続の複雑さ
- 計画書提出・認定・継続届など、専門的な対応が必要(すなわち、税理士等の認定支援機関の関与は必須とされ、継続的な対応に少なからずコスト(税理士報酬等)が掛かる)
- 制度の時限性
- 承継期限(2027年12月末)を過ぎると利用不可
- 将来的な制度改正リスク
- 猶予打切り要件や免除条件が将来変わる可能性も
8. 特例措置を使うべきケース・使わない方がよいケース
上記のメリット・デメリットを総合して見た場合、特例措置を適用すべきケースと適用しない方が良いケースとはどのようなケースでしょうか?
簡単にまとめると下表の通りになります。
| 適用を検討すべきケース | 適用を控えるべきケース |
|---|---|
| 自社株評価が高額で、相続税負担が大きい場合 | 近い将来に事業売却や清算を予定している場合 |
| 後継者が既に経営に関与している場合 | 後継者が未確定・承継意思が曖昧な場合 |
| 会社を長期的に継続する見込みがある場合 | 株式の分散や外部承継(M&A)を検討中の場合 |
また、特例措置を適用しなかった場合に生じる贈与税・相続税がそれほど大きくないケースについても、その納税猶予で得られる効果より、その後のランニングコスト(税理士報酬など)の発生により、費用負けしてしまう可能性がある点に留意が必要です。
逆に言えば、税理士・会計事務所側からすると、長期に渡り、責任をもって「管理」しなければならない案件となるわけで、少なくない負担が将来に渡り継続することになります。そのため、適正な報酬を請求することはもとより、事務所内の担当者が変わっても継続してメンテナンスできる体制を整えておく必要があります。
9. よくある質問(FAQ)
Q1:特例承継計画を提出すれば自動的に特例が受けられますか?
→ いいえ。計画提出は「申請の前提」であり、実際の贈与・相続後に認定申請を行う必要があります。
Q2:後継者が代表取締役に就任しなくても適用されますか?
→ いいえ。必ず代表者就任が条件となります。
Q3:一度承継した株式を、後継者が他者に譲渡した場合は?
→ 猶予は打ち切りとなり、贈与税・相続税が一括課税されます。
10. まとめ
法人版事業承継税制(特例措置)は、中小企業が「次の世代へバトンをつなぐ」ための非常に有効な支援制度です。
但し、適用には厳密な要件と期限があり、申請には綿密な準備が必要です。また、適用後、納税猶予を維持するのも容易ではありません。「自社株の評価」「経営継続の見通し」「後継者の意思」などを踏まえ、制度のメリット・デメリットを理解したうえで活用を検討することが重要です。
税理士からのアドバイス
まずは「特例承継計画」を令和8年3月末までに提出しておくこと。
実際の承継は後からでも構いません。期限を過ぎると特例が使えません。取り敢えず計画だけ出しておいて、適用するかどうかは後で考えるというのもアリです。
制度活用の可否は、株価評価・家族構成・将来の経営方針などを踏まえて総合判断しましょう。
【この記事の要点まとめ】
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 法人版事業承継税制(特例措置) |
| 目的 | 事業承継時の税負担軽減 |
| 提出期限 | 特例承継計画:2026年3月31日まで |
| 承継期限 | 2027年12月31日まで |
| 税猶予割合 | 贈与税・相続税100%猶予 |
| 注意点 | 廃業・譲渡で一括課税、法改正リスクあり |
| 対象に適する会社 | 自社株評価が高く、長期的に事業を継続する中小企業 |
💬 ご相談ください
事業承継税制は制度が複雑で、会社ごとの最適解は異なります。
「うちの会社は使うべき?」「今からでも間に合う?」といったご相談にも対応しています。
お気軽にお問い合わせください。